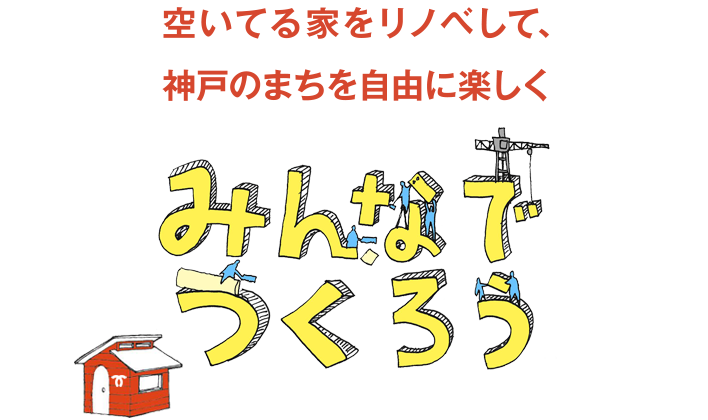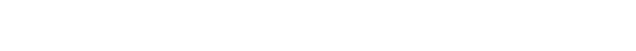前編では天井と壁の塗装作業をメインに進めてきました。今回は床の下地作りと設備関係を進めていきます。下地作りはもちろん初めて。果たしてうまくいくのでしょうか。
1.床下地の工法を考える

2Fの天井と壁は塗装ができたので、床下地作りに入っていきます。現状は全て取っ払われたスケルトン状態、まずは床下地の工法をどうするか?を決めなくてはいけません。床下地の工法は根太に直接床材を張る根太張り工法、根太に合板などを下地に張ってから床材を張る捨て張り工法、スラブ(コンクリート床)などに直接床材を張る直床工法、根太や緩衝材を間に入れ下地を張り、床板を二重にする二重床工法、といろいろな工法があり、それぞれのメリットデメリットがあります。専門家に相談したところ、「根太転がし」というアドバイスをもらいました。これはスラブに直接根太を置いていき、合板の下地を張ります。二重床工法に近い工法です。コストも安くすみますし、天井高もいっぱいまで取れそうなのでこの工法で進めていくことにしました。今回のチャレンジは建物も古く、隙間も多いので断熱や防音はしない方向で考えています。
2.作業開始、不陸をどうするか


工法が決まったので、早速材料の買い出しに出かけ、35mm角の根太と12mm厚の構造用合板を購入しました。根太を303mm間隔で転がしていきます。文章で書くと単純ですが、初心者にはこの作業でも上手く間隔を取れずサクサク進みません…。そこでスペーサーを作成し、間に挟みながら位置決めをしていくと作業がスムーズに進みました。
シンプルな根太転がし工法ですが、スラブの不陸(不陸=ふろく。床面のデコボコ)が大きい箇所も多く、水平を取ることが難しい場所が多々ありました。そこで2mm厚のベニヤ板を5cm角にカットしたものを大量に作り、不陸の大きい箇所に挟んで調整を行いました。位置が決まればコンクリート用ボンドで固定して完了です。
3.構造用合板を張っていく

次は構造用合板を張っていきます。床面を埋めていくようにサイズを測り、電動ノコギリでカットし、ビス止めを繰り返していきます。この作業もそれほど難しくなく、すぐに慣れてドンドン進めていけます。

ただ、この2Fの部屋にはシャワールームや洗面、トイレといった水回り設備を設置予定です。給排水の配管がまだ終わっていないので工務店に相談したところ、水回りのエリアは勾配配管のため、床を上げる必要があるとのこと。床の下地を全部張ってしまっても工事の際に剥がすと言われました。一気に終わらせたかったのですが、水回り設備のエリアは下地を張らず、一旦ストップすることになりました。
4.3Fの壁剥がしと壁材の張り付け


2Fは配管、設備工事を待つことになったので、次は3Fの壁に取り掛かります。とりあえず既存のベニヤ板の壁をバールでメリメリと剥がしていきます。すると壁の下地である胴縁(横方向)と間柱(縦方向、胴縁を受けるための柱)が出てきました。下地はそのまま使う予定ですが、ボロボロの部分もあるため部分的な補強が必要です。床下地の合板と同じような作業で、サイズを測りカットした後、仕上げ釘でバンバン留めていきます。こちらも電気配線が入る場所を残して張っていきました。
5.工務店とのやりとり

2Fの設備関係で工務店とのやりとりを行い、いくつかの設備機器を自分で手配することを相談しました。コンセントやスイッチの電気関係や洗面やキッチンに使う水栓などです。ユニットバスなども自分で手配は可能と言ってもらえたのですが、組み立てや設置は初心者にはそれなりに大変です。ユニットバスについては工務店に材工一式でお願いした場合の見積もりもお願いし、検討することにしました。
また、使用予定の水栓の種類なども工務店に聞かれるまで考えていませんでした。(工事の後から決めれば良いと思っていました…。)調べてみると混合栓や単水栓、壁付けや台付けなど様々な種類があります。それぞれの使用や配管のイメージまでは決まっていなかったので選択に時間がかかってしまい、思ったより時間をロスしてしまいました。
6.中編まとめ
床を作り始めると、下地だけでも塗装と同様に見た目がどんどん変わってきてテンションが上がりました。工事の関係で2Fの床の完成までいけなかったのですが、今後も楽しみになってきました。工務店とのやりとりで個人的に難しいと感じたポイントは、とりあえずでも最終に近いイメージを伝えておくことでした。電源コンセントやスイッチの位置、天井の照明の位置やイメージ、水栓の種類、配管のことなどの細かい部分です。慣れもあると思いますが、こうしたことがスムーズに進めて、かつイメージした仕上がりにするには重要なポイントだと思います。
完成目標としている3月いっぱいまで、かなり時間がなくなってきました。これからどんどん追い込んでいきます!次回もお楽しみに!